
こんにちは。よっしーです(^^)
本日は、Go言語のよくある質問について解説しています。
背景
Go言語を学んでいると「なんでこんな仕様になっているんだろう?」「他の言語と違うのはなぜ?」といった疑問が湧いてきませんか。Go言語の公式サイトにあるFAQページには、そんな疑問に対する開発チームからの丁寧な回答がたくさん載っているんです。ただ、英語で書かれているため読むのに少しハードルがあるのも事実で、今回はこのFAQを日本語に翻訳して、Go言語への理解を深めていけたらと思い、これを読んだ時の内容を備忘として残しました。
起源
このプロジェクトの目的は何ですか?
2007年にGoが構想された当時、プログラミングの世界は今日とは異なっていました。本格的なソフトウェアは通常C++やJavaで書かれており、GitHubは存在せず、ほとんどのコンピューターはまだマルチプロセッサではありませんでした。そして、Visual StudioやEclipse以外には、IDEやその他の高レベルなツールはほとんど利用できず、ましてやインターネット上で無料で入手できるものはありませんでした。
一方で、私たちは当時使用していた言語とそれに関連するビルドシステムで大規模なソフトウェアプロジェクトを構築するために必要な過度な複雑さにフラストレーションを感じていました。C、C++、Javaなどの言語が最初に開発されてからコンピューターは驚くほど高速化していましたが、プログラミング行為自体はそれほど進歩していませんでした。また、マルチプロセッサが普遍的になることは明らかでしたが、ほとんどの言語はそれらを効率的かつ安全にプログラムするためのサポートをほとんど提供していませんでした。
私たちは一歩下がって、技術が発展する中で今後数年間ソフトウェアエンジニアリングを支配する主要な問題は何か、そして新しい言語がそれらの問題にどのように対処できるかについて考えることにしました。例えば、マルチコアCPUの台頭は、言語が何らかの並行性や並列性に対する第一級のサポートを提供すべきであることを示していました。そして、大規模な並行プログラムにおいてリソース管理を扱いやすくするために、ガベージコレクション、または少なくとも何らかの安全な自動メモリ管理が必要でした。
これらの考慮事項は一連の議論につながり、そこからGoが生まれました。最初はアイデアと要求仕様の集合として、その後言語として。包括的な目標は、Goがツールを可能にし、コードフォーマットなどの日常的なタスクを自動化し、大規模なコードベースでの作業の障害を取り除くことによって、実際に働くプログラマーをより支援することでした。
Goの目標とそれらがどのように満たされているか、または少なくともどのようにアプローチされているかについてのより詳細な説明は、「Go at Google: Language Design in the Service of Software Engineering」という記事で読むことができます。
解説
この節では、Go言語が生まれた背景と目的について説明されています。重要なポイントをいくつか解説します。
時代背景の違い 2007年当時と現在では開発環境が大きく異なっていました。GitHubのような協業プラットフォームもなく、今では当たり前のマルチコアプロセッサも普及していませんでした。この時代背景を理解することで、なぜGo言語が特定の機能を重視して設計されたかが分かります。
既存言語への不満 Go言語の開発者たちは、C++やJavaでの大規模開発における複雑さに課題を感じていました。「コンピューターは高速化したのに、プログラミング自体はそれほど進歩していない」という指摘は、言語設計における重要な動機となっています。
並行処理への着目 マルチコアCPUの普及を見越して、Go言語は最初から並行処理を「第一級市民」として扱うよう設計されました。これが、GoのGoroutineやChannelといった特徴的な機能につながっています。
開発者体験の重視 「実際に働くプログラマーを支援する」という目標は、Go言語の哲学を端的に表しています。コードフォーマットの自動化(gofmt)や、シンプルで理解しやすい文法などは、この思想の現れです。
おわりに
本日は、Go言語を効果的に使うためのガイドラインについて解説しました。

何か質問や相談があれば、コメントをお願いします。また、エンジニア案件の相談にも随時対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
それでは、また明日お会いしましょう(^^)
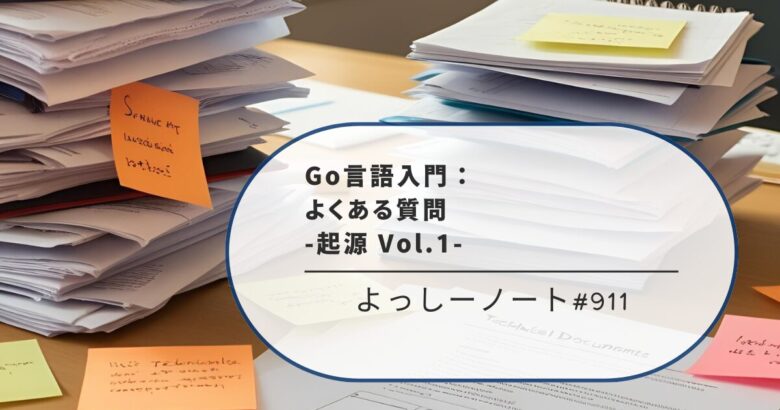

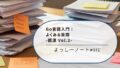
コメント